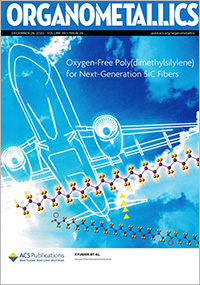-
2025/10/24
炭化ケイ素連続繊維誕生50周年記念講演会
趣旨:東北大学金属材料研究所の故矢島聖使教授のグループが炭化ケイ素連続繊維の製造方法を発明し、その成果を初めて論文として発表してから2025年で50年になる。公益財団法人特殊無機材料研究所(以下 本研究所と記す)は、この機会に50周年記念講演会を開催して、当時の研究から現在の商業化にいたるまでの研究開発状況を振り返り、今後の研究開発の方向について指針を考える機会を設けたいと考える。
本研究所は、世界に先駆けて研究開発された有機ポリマーを前駆体とする炭化ケイ素連続繊維の高度化ならびに工業化を目的にして1976年3月、文部省所轄の財団法人として設立され、2011年6月に内閣府所轄の公益財団法人への移行が認定され、現在に至っている。その間、独自に研究開発を行うとともに、企業各社の炭化ケイ素連続繊維の工業化を支援してきた。最近では、大学、研究機関の研究支援を中心に活動している。
高度な先進工業材料である炭化ケイ素連続繊維の製造技術は純国産技術である点が重要であり、炭化ケイ素連続繊維の企業各社による事業化により、それを用いた複合材の開発が国際的に注目されて、海外を中心に発展してきた。中でも、CMC(炭化ケイ素連続繊維/炭化ケイ素母材複合材料)の実用化は、国産の高性能・高純度の炭化ケイ素連続繊維なしには果たされなかったと考えられる。
このように、炭化ケイ素連続繊維の周辺技術開発は、今後も国際的競争が激しくなると予想される中で、我が国の今後の研究開発の方向性(戦略)を考えることは極めて重要と思われる。このような趣旨で以下のように50周年記念講演会を開催する。主催:公益財団法人特殊無機材料研究所
日時:2025年12月10日(水)13:30~16:55
会場:一橋講堂1階特別会議室101、102(東京都千代田区一ツ橋2-1-2)
参加費:無料13:30~13:35 開会の挨拶
13:35~14:25
市川 宏(有明セラコ株式会社)
「SiC繊維ニカロンと複合材の研究開発史」14:25~15:05
朝倉 勇貴(株式会社IHI)
「炭化ケイ素複合材料を用いる航空機エンジン開発の現状」15:05~15:30 休憩
15:30~16:10
吉田 克己(東京科学大学)
「SiCf/SiC複合材料の原子力および核融合炉用材料としての期待(仮題)」16:10~16:50
久新 荘一郎(特殊無機材料研究所)
「炭化ケイ素材料の研究開発に対する基礎化学からのアプローチ」16:50~16:55 閉会の挨拶
申し込み方法:電子メールに氏名、所属、電話番号、電子メールアドレスを記載の上、以下の申し込み先にお送りください。
申し込み期限:2025年12月5日(金)
申し込み先:〒376-8515 群馬県桐生市天神町1-5-1 群馬大学桐生キャンパス内
公益財団法人特殊無機材料研究所事務局
電話:0277-22-8552(月金のみ)、電子メール:jimu(at)aims.or.jp((at)は@に置き換えてください。)
-
2025/05/26
公益財団法人特殊無機材料研究所 研究助成募集要項(2025)
助成対象:炭化ケイ素および特殊無機物質に関する以下のような研究
・炭化ケイ素繊維の合成、構造、性質などに関する研究
・炭化ケイ素および関連物質に関わる科学技術に関する研究
・炭化ケイ素および関連物質を合成するための新規前駆体ポリマーの開拓
・新たなコンセプトをもつ物質の提案およびその合成法、構造、物性、用途に関する研究助成金額:1件50~100万円
応募方法:研究助成申請書に記入し、7月31日(木、必着)までに以下の提出先に電子メールで提出する。
提出先 :〒376-8515 群馬県桐生市天神町1-5-1 群馬大学桐生キャンパス内
公益財団法人特殊無機材料研究所事務局
電話:0277-22-8552、電子メール:jimu(at)aims.or.jp((at)は@に置き換えてください。)採択後 :2026年3月末に報告書を提出し、研究発表会(2026年5月に開催)で研究成果を発表していただきます。
-
2024/10/30
特殊無機材料研究所講演会
主催:特殊無機材料研究所
協賛:日本化学会、日本セラミックス協会(申請中)、粉体粉末冶金協会
分野:炭化ケイ素繊維および関連する耐熱材料の研究開発
日時:2024年12月18日(水)14:00~17:15
場所:学士会館3階302号室(東京都千代田区神田錦町3-28)14:00~14:05 開会の挨拶
14:05~14:45
小谷 政規(宇宙航空研究開発機構(JAXA))
「セラミックス基複合材料(CMC)の航空エンジンへの更なる適用に向けた研究開発」14:45~15:25
舩津 賢人(群馬大学大学院理工学府)
「プラズマジェットを利用した耐熱材料の加熱試験とその光学計測」15:25~15:50 休憩
15:50~16:50
吉見 享祐(東北大学大学院工学研究科)
「モシブチック合金の研究開発とマテリアルズ・インフォマティクス」16:50~17:10
澁谷 昌樹(新潟ファーネス工業株式会社)
「炭化ケイ素系多孔質部材による加熱炉の省エネルギー化」17:10~17:15 閉会の挨拶
参加費:無料
申し込み方法:電子メールに氏名、所属、電話番号、電子メールアドレスを記載の上、以下の申し込み先にお送りください。
申し込み期限:2024年12月13日(金)
申し込み先:〒376-8515 群馬県桐生市天神町1-5-1 群馬大学桐生キャンパス内
公益財団法人特殊無機材料研究所事務局
電話:0277-22-8552(月金のみ)、電子メール:jimu(at)aims.or.jp((at)は@に置き換えてください。)
-
2024/08/01
総説の発表と実用新案の登録
特殊無機材料研究所研究員の澁谷昌樹博士の研究成果が総説として発表されました。また、実用新案に登録されました。
総説
澁谷昌樹,田渕直人,田渕義也,阿部浩典,炭化けい素系多孔質部材による加熱炉の省エネルギー化,工業加熱 2024, 61, 15–19.実用新案
渋谷昌樹,加熱装置,登録第3246632号,令和6年4月30日登録.以上
-
2024/06/14
公益財団法人特殊無機材料研究所 研究助成募集要項
助成対象:炭化ケイ素繊維および関連する特殊無機材料の研究開発。特に、
・耐熱性などの物性の高性能化
・構造や物性に関する研究開発
・新たな用途に関する研究開発
・新規耐熱材料の研究開発助成金額:1件50万円
応募方法:研究助成申請書に記入し、9月20日(金、必着)までに以下の提出先に電子メールで提出する。
提出先 :〒376-8515 群馬県桐生市天神町1-5-1 群馬大学桐生キャンパス内
公益財団法人特殊無機材料研究所事務局
電話:0277-22-8552、電子メール:jimu(at)aims.or.jp((at)は@に置き換えてください。)採択後 :2025年3月末に報告書を提出し、研究発表会(2025年5月に開催)で研究成果を発表していただきます。
-
2023/11/20
特殊無機材料研究所研究発表会
日時:2023 年 12 月 12 日(火)14:15~16:50
場所:学士会館 3 階 310 号室(東京都千代田区神田錦町 3-28)14:15~14:20 開会の挨拶
14:20~14:40(Zoom による発表)
「ヤヌスナノシートにより形成された液-液二相系反応場を用いた有機反応」
(早稲田大学先進理工学部応用化学科)菅原 義之
https://gunma-u-ac-jp.zoom.us/j/82532379312?pwd=pkIEL0ARzPB5DEA4PakdjlmJcTQRC1.1
ミーティング ID: 82532379312、パスコード: 96287914:40~15:00
「直交三次元織物 SiC 繊維/SiC 複合材料の高温・大気中における疲労き裂進展挙動」
(東京農工大学大学院工学研究院先端機械システム部門)小笠原 俊夫15:00~15:20
「SA チラノ繊維、SA チラノヘックスにおける繊維断面組織の STEM 観察」
(大阪産業技術研究所応用材料化学研究部)尾崎 友厚15:20~15:40 休憩
15:40~16:00(Zoom による発表)
「電気泳動堆積(EPD)法により形成した h-BN 界面層を有するバンドル SiCf/SiC 複合材料の作製
とその機械的性質」
(東京工業大学科学技術創成研究院ゼロカーボンエネルギー研究所)吉田 克己
https://gunma-u-ac-jp.zoom.us/j/82532379312?pwd=pkIEL0ARzPB5DEA4PakdjlmJcTQRC1.1
ミーティング ID: 82532379312、パスコード: 96287916:00~16:20
「炭化ケイ素多孔体の形成初期過程の観察」
(愛媛大学大学院理工学研究科理工学専攻)山室 佐益16:20~16:40
「無酸素炭化ケイ素繊維、高分子量ポリカルボシラン、CMC マトリクスの研究」
(群馬大学大学院理工学府分子科学部門・特殊無機材料研究所)久新 荘一郎16:40~16:45 閉会の挨
-
2021/04/01
久新 荘一郎 教授の無酸素ポリシランの論文が、米国化学会誌、Organometallicsの2020年39巻24号、12月28日に発表され表紙を飾りました。
題目: Oxygen-Free Poly(dimethylsilylene)
Soichiro Kyushin, Kazuto Mizoguchi, Tomohiro Tanaka, Takeshi Yamanobe and
Kenichi Hayashi
概要:近年、SiC/SiCセラミックマトリックスコンポジット(CMC)が高性能航空機エンジンの主要部品として採用されているため、炭化ケイ素繊維が注目を集めています。出発物質として無酸素ポリ(ジメチルシレン)を用いて性能を向上させることが期待されます。この研究では、無酸素ポリ(ジメチルシレン)の合成と特性評価が発表されています。
掲載誌:Organometallics, 39(2020) 4651-4656